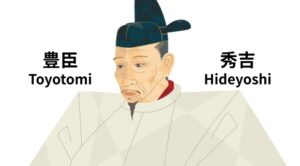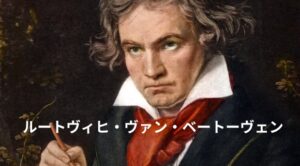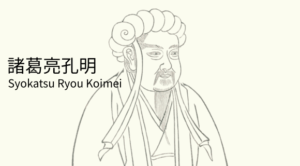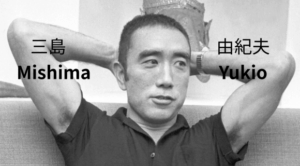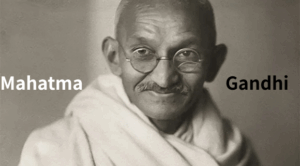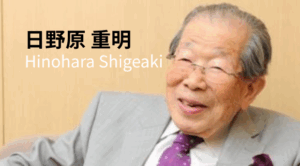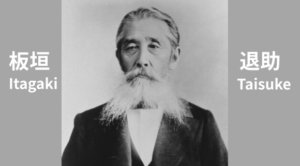無欲は、、、
無欲は怠慢の基である。
資本主義社会においては「無欲」ではダメなのだと思います。正しい欲望を持つことも大切です。私自身は「欲」というよりも、あえて物質的な欲を自分の目の前においてそれを掴むための努力をするべきなのではないかと考えています。「馬ニンジンを自分の前にぶら下げる」ということでしょうか??
すべて世の中のことは、、、、
すべて世の中のことは、もうこれで満足だという時は、すなわち衰える時である。
「現状維持は衰退の始り」ということなのでしょうか?常に高い目標を持ち前進することが肝心なのではないかと思わされる言葉ですね。
成功や失敗のごときは、、、
成功や失敗のごときは、ただ丹精した人の身に残る糟粕(そうはく)である。
つまるところ、失敗や成功など問題ではなく、その過程にこそ価値があるということなのでしょう!!失敗や成功するかを恐れずに道を努力して歩むことこそが尊いのだと!!
四十、五十は洟垂れ小僧、、、
四十、五十は洟垂れ小僧、六十、七十は働き盛り、九十になって迎えが来たら、百まで待てと追い返せ。
「60歳や70歳は働き盛り??」なんと元気の出る言葉かなと、、、人生100年時代に最もふさわしい言葉でなないかと今更ながらに思わされる名言ですね。
事業には信用が第一である。、、、
事業には信用が第一である。世間の信用を得るには世間を信用することだ。個人も同じである。自分が相手を疑いながら、自分を信用せよとは虫のいい話だ。
「世間は正しい」とは、松下幸之助氏の「道をひらく」にもあるように、世間は正しいと信じなければ世間から信用されることはないということである。組織の中ではお互いを信じ合えることが肝心なのではないでしょうか?
論語とソロバンという、、、
論語とソロバンというかけ離れたものを一つにするという事が最も重要なのだ。
営利目的の事業を金儲けの道具とするのではなく、道徳である論語を事業に組み込めないかと考えた名言である。
できるだけ多くの人に、、、
できるだけ多くの人にできるだけ多くの幸福を与えるように行動するのが我々の義務である。
私たち会社の義務はできるだけ多くの人に幸せを与えることなんだと改めて考えさせられる言葉ですね。
長所を発揮するように努力すれば、、、
長所を発揮するように努力すれば、短所は自然に消滅する。
どうしても短所が気になるのが常ですが、相手の長所を伸ばしてやることで、気になる短所をなくすこともできるのではと思い直しました。
他人を押し倒してひとり利益を獲得するのと、、、
他人を押し倒してひとり利益を獲得するのと、他人をも利して、ともにその利益を獲得するといずれを優れりとするや。
この時代から「WIN-WIN」の考え方が出来ていたのだと再認識させられる言葉です。
言葉は真心を込め、、、
言葉は真心を込め、行いは慎み深く、事を取りさばき、人に接するには必ず誠意を持って臨め。
改めて「真心」や「誠意」を持って行動に努めなければならないと言うことです。
「論語と算盤」現代版
第1章 処世と信条
昔、菅原道真は「和魂漢才」という「日本独自の精神と、中国の学問」を併せ持つことが大事であると言いました。渋沢栄一は「士魂商才」という言葉を残しています。「武士のような心で、商売をする」つまりこれが、「論語と算盤」の基礎になっているのです。当時西洋文化が入ってきたわけですが、欧米諸国の日々進歩しる新しいものを研究することも大事だが、東洋古来の古いものの中にも捨てがたいものがあるということです。
第2章 立志と学問
学問を学ぶことは「立志」のためであることなのだが、何事も最初から仕事を任せてもらえることはありません。「千里の道も一歩から」であり、天下を取った豊臣秀吉ですら信長の「草履とり」から初めているのです。つまらない仕事であったとしても与えられた仕事を、その時の余命をかけて真面目にやれないものは出世できるはずがないということです。
第3章 常識と習慣
渋沢栄一が言うところの「常識」とはどういうものなのか?これが書かれています。
「常識とは、智・情・意の3つがそれぞれバランスを保って、均等に成長したものが完全な常識である」と言っています。「智」とは、知恵のことであり、学問によって得られるものである。まずは何をすべきかを理解できる「智」が必要です。しかし、この「智」ばかりが先行すると人を突き飛ばしてでも何かを成してしまう人間になると言っています。それを補う形で、「情」がなければなりません。
「情」は一種の緩和剤で、何事もこの「情」が加わることによってバランスを保つことができます。
しかし、「情」は欠点もあり、流されてします危険性があると言っています。
その感情に流されないでいるために「意」というものが必要だと言っています。
「意」は精神活動の大本とも言えるものであり、強い意志さえあれば、人生に置いて大きな強みを持つことになる。
第4章 仁義と冨貴
経済活動において、利益を得ようとすることと、社会正義のための道徳にのっとるということは、両者がバランスよく並びたってこそ、初めて国家も健全に成長する。そして、個人もちょうど塩梅よく富を築いていくのである。
その中で、個人の富について触れている。
いかに自分が苦労して作った富だとはいえ、自分一人のものだと思うのは大きな間違いである。
「高い道徳を持った人間は、自分が立ちたいと思ったら、まずは他人を立たせてやり、自分が手に入れたいと思ったら、まずは人に得させてやる」とこの本では書かれています。つまり、利益が欲しいという思いがまさって、下手をすると富を先にして道義を後にする弊害が生まれてしまうのです。
第5章 理想と迷信
ある書物に「もし年老いてまだ寿命に恵まれていたとしても、ただ食べて、寝て、その日を送るだけの人生では、そこには生命などなく肉の塊があるだけだ。一方で年老いても体が満足に動かなくなっても、心だけは世の中の役に立とうとするなら、それは生命ある存在になる」とあります。
本の中では「趣味」についても触れています。どんな仕事や、することでも、自分のやるべきことに深い「趣味」を持って努力する必要性を説いています。
孔子の言葉に「理解することは、愛好することの深さに及ばない。愛好することは楽しむ境地の深さに及ばない」という言葉も紹介されています。
第6章 人格と修養
人格の基準として、「人は動物と異なる点がある。それは、道徳を身につけ、知恵を磨き、世の中のためになる貢献ができるという点だ」と言っています。
人の評価というものは、「成功か失敗か」を論じるのではなく、よくその人が社会のために尽くそうとした精神と効果とによてt、行われるべきであると述べられています。